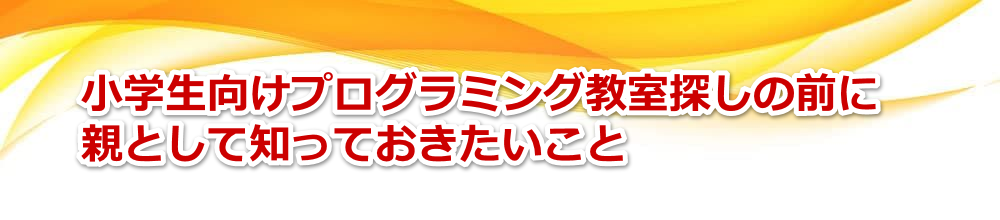
小学生向けオンラインプログラミングの始め方
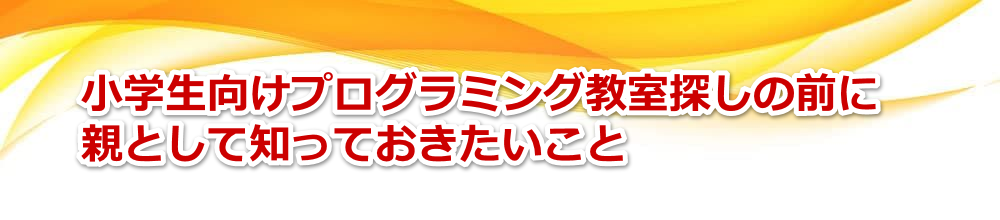
プログラミング教育でコンピューターを学ぶことの意義
子どものうちからコンピューターを学ぶことには賛否両論あります。
「もっと他に勉強することがある」「これからはコンピューターぐらいあたり前」など。
ここでは子どものうちからコンピューターを学ぶことの意義であまり言われることがないものを紹介してみたいと思います。
ガマン強さを学べる
子どものうちは上手くいかない(できない)ことが多いものです。そんなときに、イライラして大きな声を出したり、不機嫌な態度を見せると、先生(周りの大人)が手助けしてくれます。
- どうしたの?
- 何ができないの?
- 何か困ってることがあるの?
悪いことではないように思えますが、これだと自分で解決しようという気持ちが薄れてしまいます。騒げば先生(親)がやってくれる。そう思ってしまいます。
ただ、大人になってもそうでは困ります。
学校にいるあいだは騒げば先生が助けてくれるかもしれませんが、社会に出れば自分で解決するしかありません。
誰かに助けてもらう(手伝ってもらう)ことはできますが、イライラを見せてるだけで手を差し伸べてくれる人はいません。そんな人とは関わりたくないと思われるだけ。
イライラしてれば誰かが助けてくれる学校とは社会は違うのです。
コンピューターは空気を読まない
イライラしてれば助けてもらえるのは周りが空気を読んでいるから。
ところが、コンピューターは空気を読みません。
イライラしてキーボードを強くたたいたところで答えは同じ。
思い通りにならないからと言って相手にあたっても意味がありません。
思い通りにならないときこそ冷静になる。
そのことを学べるのがコンピューターです。
コンピューターは誰に対しても平等です。
「声の大きい人」のほうに優先的に答えるなんてことはありません。
「騒いだもの勝ち」を許さないのがコンピューターです。
こうしたことを小さいうちに経験しておくことは決して悪いことではありません。
